勝敗を左右する指標は、変化するもの。
戦略とは、勝利につながる指標を、いかに選ぶか。
- リーダーが現場を、直接見聞きすることも必要。
最前線・現場のフィードバックを受けるために。 - 人事・技術・運用において、創造的破壊を。
「経験・練磨」に重きを置くか。
「分析・試行錯誤」に重きを置くか。
書籍『「超」入門 失敗の本質』
著者 鈴木博毅さん
出版社 ダイヤモンド社
出版 2012/4
ISBN978-4-478-01687-9

今回はこちらでお勉強。
書籍『失敗の本質』の入門書。
書籍『失敗の本質』
第二次世界大戦時における、日本軍の組織論を分析。
日本人特有の、文化論的側面も。
初版は、1984年に発行。
読み継がれている本。

内容、難しいとか。
なので、入門書を読んでみることに。
戦略とは、「目標達成につながる勝利」を選ぶこと

「目標達成につながる勝利」。
「有効な指標」と言えるとか。
「目標達成につながる勝利」と、「目標達成につながらない勝利」を選別。
目標達成につながる勝利を、選び取ること。

第二次世界大戦での日本軍。
戦略があいまいなこと、多々。
戦略を実現する方法

検索AI、perplexityによると。
戦略:マクロ的視点、長期的計画、全体的な方向性
戦術:ミクロ的視点、短期的行動、具体的な実行手段
戦術で勝利しても、最終的な勝利は得られず。
「目標達成につながらない勝利」が存在
日本軍が駐留していた、南西諸島25の島。
米軍が上陸占拠したのは、8島のみ。
残りの17島は、戦力を無力化しただけ。
米軍の侵攻を阻止する、役割を果たせない拠点。

日本軍。
約70%もの不要な場所に、戦力を。
戦力の無駄遣い。
日本軍:目標達成につながる勝利が、少なかった
米軍:目標達成につながる勝利が、多かった
間違った方向性での努力は、報われず。

目的達成のために。
押さえるべきところさえ、押さえれば。
100点を取らずとも。
資源は有限。
自分の資源の振り分け、重要。
パレートの法則によると。
80点を取るのには、2割の時間で済み。
80点を100点にするには、残り8割の時間がかかるとか。

力の入れどころ、抜きどころを見極めて。
的を絞り、選択・集中。
合格点が取れれば、OK。
それ以上は求められていない、オーバースペックになりかねず。
オーバースペックの部分は、供給側の自己満足になりがち。
顧客には、差がわからず。
そこまでの需要ないことがほとんど。
例えば、90点と91点のラーメン。
どちらも、美味しいラーメン。
「過ぎたるは、及ばざるが如し」
ビジネスだと、ニーズの有無が重要とのこと。
需要がないところで頑張っても、報われず。
指標:勝利を左右する要因
追いかける指標を決めること。

押さえるべき事を、決定。
- 「成功体験のコピー・拡大」は、戦略ではなく。
- 効果を失った指標を追うと、やがて敗北へ。
日・米軍の、指標発見の違い
- 有効な指標を、経験則から偶然、発見
- 勝利に内在する指標を理解していないので、再現性がない
- 成功体験のコピーに陥る
- 一点突破、成功体験を全面展開

日本軍は、優先順位が定まっておらず。
足元を固めないまま、戦線拡大。
勝った戦闘のやり方を、そのまま全面展開。
ワンパターン化。
対策を打たれて、敗北へ。
- 敵・味方の行動と結果を分析
- 常に有効な指標を模索しており、勝利に再現性がある
- 空母、輸送船の撃沈
- 無意味な戦闘は避ける

米軍は優先順位をしっかり設定。
・敵空母は、移動基地で脅威。
落とせば、制海権・制空権獲得に有利。
・敵輸送船を落とせば、兵糧攻めに。
補給線が伸びた日本軍に、有効。

結果の検証・総括の有無。
次に活かす・成功の再現への、大きな差に。
日・米軍の戦い方の違い
練磨・改善により達人を生み出す

型を反復練習し、型を超える発想。
守・破・離。

変化には弱く。
型にはまれば、強いものの。
既存の戦闘を無力化する、新モデルを生み出す

イノベーション。
常識を変えてしまうような。
有効な指標は、変わっていくもの
有効な指標を見抜き、行動の方針にすること

方向性、大事。
「今、何で、勝負しているのか?」
「今、何が勝利条件なのか?」

指標を変えることで、物事を有利に運ぶことも可能。
指標変化の例:米軍の、零戦への対応
- 軽量故の、優れた空戦能力。
防弾性能を犠牲にしているものの。 - エース級パイロット多数。
猛訓練により。

零戦。
高い空戦能力。
避けまくって、当てまくる?
「当たらなければ、どうということはない。」
スペシャリストの、スキル頼り。
米軍、苦戦していたものの。
装備面・運用面の方針を変え、対応。
操縦技能が低いパイロットでも勝てるように。
飛行機の開発と、戦術の考案。
装備面(技術)
▪️索敵:レーダー開発
・敵の「偵察機での索敵・奇襲」を無効化
▪️防御:防弾性能向上させ、生存率UP
・新エンジン開発。
重武装・高い防弾性を実現。
飛行速度を保ちつつ。
▪️攻撃:かすれば爆発する、砲弾の開発
・以前は直撃させる必要あり。
攻撃が、点から範囲へ。
運用面
▪️零戦1機に対して、米軍機は2機で戦闘
・1対2の状況を。
かつ、1機がおとりに。
連携で勝負

米軍。
索敵能力向上で、素早く戦闘準備。
防御は、被弾に耐え。
攻撃は、当たりやすく。
連携作戦で、有利な状況に。
個の力に頼らず勝てる、仕組みを実現。
チーム層を、厚くするような。

米軍は、勝負のルールを変更。
達人頼りの空戦能力ではなく。
「達人を不要とするシステム」を作って。
仕組みを変え、再現性を持たせつつ。
有効な指標の把握には、現場のフィードバックが必要
ダブル・ループ学習で、変化に対応
「想定した目標と問題自体が、違うかも」という、疑問・検討を含めた学習スタイル。
目標や問題の基本構造そのものを、再定義・変革することも。
現場が直面している問題を、対策決定者が正確に理解していることが前提。

時には常識を疑って。
ゼロベースで検討も。

「問題構造は、変数」と考えて。
「0→1」、「開発」に向く?

米軍は、ダブル・ループ学習を活用。
シングル・ループ学習に、偏りすぎないように
「目標や問題の基本構造が、自分の想定と違う」と思わない学習スタイル

「問題構造は、定数」と考えて。
「1→10」、「発展・高性能化」に向く?

日本軍は、シングル・ループ学習。
成功体験を、練磨。
型にハマっている間は、目覚ましい成果をあげるものの。
- 成功した指標が、曖昧。
- 適用する範囲を、判断しにくい。
- 過去の成功体験の繰り返しになりやすく、長期間は生き残れない

ダブル・ループ学習は、イノベーションを目指して。
シングル・ループ学習は、ハイスペックを目指して。
どちらにも良さはあり。
創造的破壊の要因:人事・技術・運用
創造的破壊は、それまでの戦い方を無効に。

イノベーションは、非連続的に起こると聞きます。
ゲーム・ルール自体が変わる程。

例えば。
スマホの登場で、ガラケーは衰退。
人事
「ヒトと組織」の極めて柔軟な活用による、自己革新。
適材適所。
信賞必罰。

米軍は、新陳代謝しっかり。
結果を出せない指揮官は交代。
逆に。
日本軍は、硬直した組織。
幹部の言葉は絶対。
間違っていても。
結果を出せずとも、そのまま。
技術
「新技術」の開発による、自己革新。

米軍の零戦対策。
重武装、砲弾・レーダー開発。
運用
「技術の運用」による、自己革新。
技術だけでなく。

米軍の零戦対策。
戦闘は、1対2で。
イノベーション
支配的な指標を差し替える、「新しい指標」で戦うこと
「高性能」と「イノベーション」は、本来別物。
偶然重なることがあるものの。
イノベーション創造の3ステップ
- 支配的な「既存の指標」を、発見
- 支配的な指標を、「無効化」
- 支配的だった指標を超える、「新たな指標」で戦う

相手の強みを発揮させず。
自分の強みは活かして。
計画的なイノベーション
- 既存の指標を見抜く
- 既存の指標を無効化する、新たな指標を見出す。
ダブル・ループ学習で。
現場を活用できる組織は強い
- 上層部と現場の意見交換がある。
- 現場からのフィードバックがある。

規制が緩い方が、イノベーションは起こりやすいもの。
現場の自由。
米軍は、成果が最大化。

米軍。
現場のフィードバックを受けるために。
作戦本部と現場の人材の入れ替えを、定期的に。
組織に良い緊張感を維持。
一方で。
- 上層部の独断
(状況にかかわらず、成功体験の繰り返しを求めがち) - 現場・専門家の意見を聞かず、押さえつけがち。
(フィードバックを受けようとしないので、判断材料にも事欠く。)
日本軍は、成果を潰しがち。

良い意見も、上層部の思惑と違えば、封殺。
人事評価と配置は、組織が発する重大メッセージ
組織の「限界」と「飛躍」を決める要素
課題と配置人材の最適化を図るべき
トップが、メンバーが生み出した成果をどう評価して、その人物をどう扱うか
成果を出すため、皆、必死に。
成果を出さないと、クビになることもあるので。

新陳代謝も進みやすく。
能力主義に。
保身・無責任が蔓延していくことに。

やってもやらなくても変わらないなら。
事なかれ主義に陥りがち。
リーダーは、新たな指標を見抜くことが求められる

リーダー。
「判断」が重要な仕事。
組織の発展・衰退は、リーダー次第?
リーダーが現場入りすることで、状況を正確に把握
正確な状況把握が必要。

問題を解決するには。
まず、問題の把握から。
意外と、認識できていないもの。
- 情報の歪みを回避
- 決定権者が問題を直接知ることで、改善スピードUP
- 誤った方向性になっていないかの確認に
- 新たな気付きを得るチャンスに
- 現場のアイデアを、直接リーダーが検討可能
人づての情報は、脚色が入る

伝言ゲームがあるくらい。
人の忖度や感情が入り、情報に歪みが。
Amazon創業者ジェフ・ベゾスさんによると。
2枚のピザを分け合える程度(約5~8人)の少人数チームが、最も効率的。
効率的なプロジェクト管理や、イノベーション促進に役立つとか。
【少人数チームのメリット】
- 失敗を恐れず挑戦できる環境に。
メンバー間の信頼が深まりやすいので。 - 生産性を高く維持。
「集団思考」「社会的怠惰」を防止して。

風通しの良い組織が理想。
意思決定から行動への速さは、重要。
アイデア止まりは、無価値と聞きます。
行動を伴ってこそ、変化が。
リスクは周知して、対策・管理
周知することで、注意を払う人が増え。
備えることもでき、リスク減少に。
リスクは、放置してもなくならず。
放置するほど、発生確率は上がりがち。

物事、大ごとになる前に対応する方が簡単。
予防の意識。
「起こさせない」
「被害を最小限にする」
想定外の悪いことは、いつかは起こるもの。
まとめ
勝敗を左右する指標は、変化するもの。
戦略とは、勝利につながる指標を、いかに選ぶか。
- リーダーが現場を、直接見聞きすることも必要。
最前線・現場のフィードバックを受けるために。 - 人事・技術・運用において、創造的破壊を。

「批判という風を入れよ」とは、ニーチェの言葉。
組織の風通しを良くするのは、永遠の課題?
「経験・練磨」を重視するか。
「分析・試行錯誤」を重視するか。
第二次世界大戦における、日・米軍の強み
- 経験によって、偶然生まれるイノベーション
- 練磨の極限を目指す文化

ハマれば強いが、アドリブ効かず。
- 戦闘中に発見した、「指標(戦略)」を読み取る高い能力
- 相手の指標(戦略)を明確にし、それを差し替えるイノベーション

分析をもとに。
戦い方を変化。
前提を変えてしまうような。
後々、自分の有利な状況へ。
反面教師、日本軍司令部の行動
- 都合の悪い情報は無視
- 成功体験に固執し、間違った勝利条件を現場に強要
- 適切な人事をせず

成功法は様々。
個人の適性もあり。
でも、失敗の本質は、似通っていると聞きます。
想定外の変化に対応したものが、生き残る
変化に対応できるよう、自分をアップデートしていきたいものです。

興味を持たれた方は、是非、原著もご一読を。

本家『失敗の本質』はこちら。
著者
戸部良一さん
寺本義也さん
鎌田伸一さん
杉之尾孝生さん
村井友秀さん
野中郁次郎さん

「分析し、勝てる指標を、選び取る。」
人生を、もっと楽しく、快適に。
では、ありがとうございました!
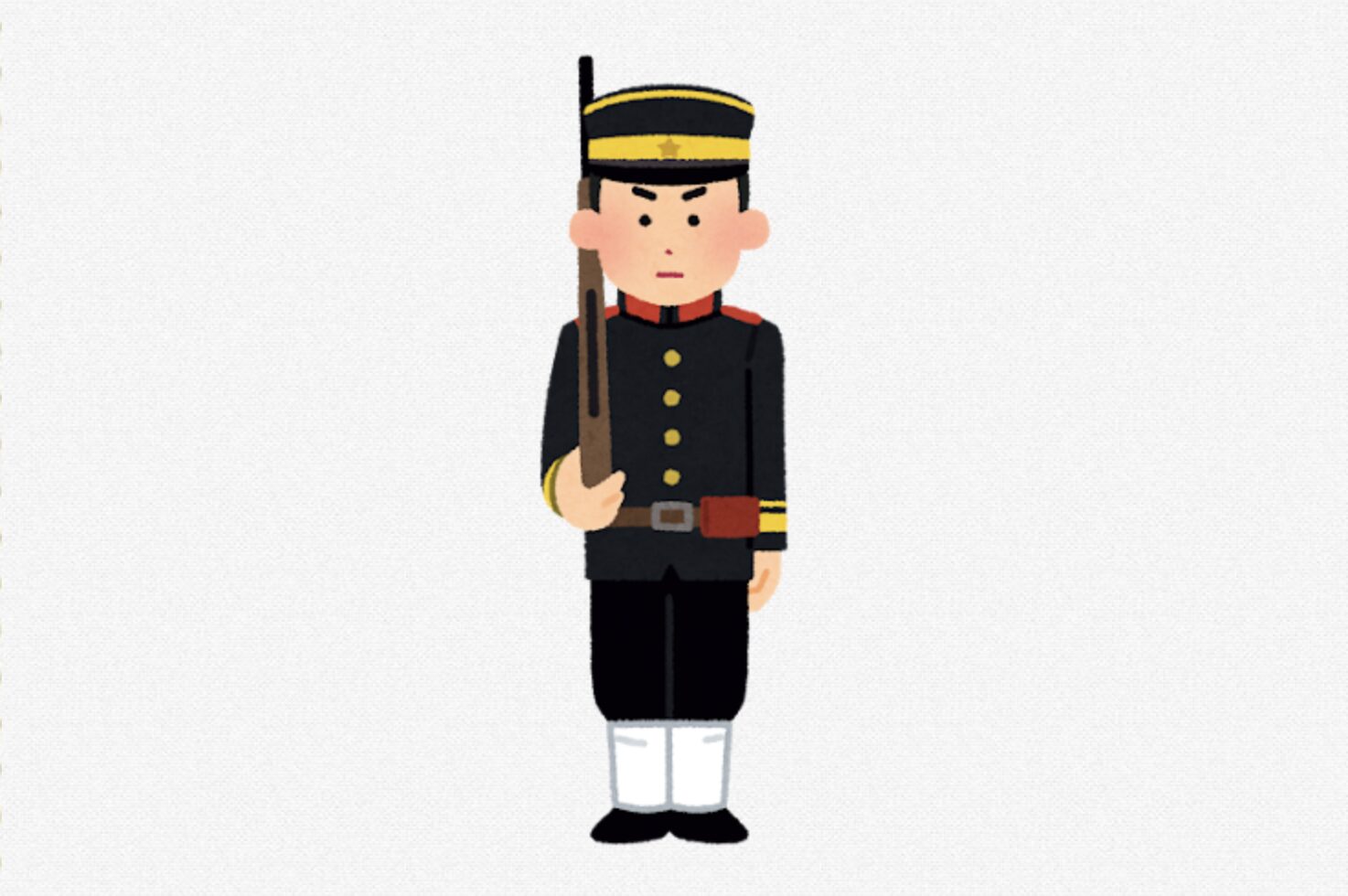


コメント