成果 = 力量 × 実行力
実行しなければ、成果は0。
才能・知識・アイデアが優れていても。

行動に移さなければ、いいアイデアも、ゴミのままだとか。
実行力は技術。
資質ではなく。
・決心
・実行
・維持

必ずやるべき目標を立てて。
とにかく行動・実践。
できるまでやりましょう!
書籍『「後回し」にしない技術』
著者 イ・ミンギュさん
(心理学博士・臨床心理専門家)
訳 吉川 南さん
出版社 文響社
出版 2021/1/19
ISBN978-4-86651-333-1
今回はこちらでお勉強。
決心する
・プロセスを「見える化」する
・本当の問題を見つける
・逆算スケジューリングを取り入れる
・どんな時も、「代案」を用意
・公開宣言効果を利用
・切実な理由を探す
プロセスを「見える化」する
・スタート・モチベーション
・持続モチベーション
スタートモチベーション
目標を達成した状態をイメージすること
持続モチベーション
目標までのルートを正しくとらえること
ある方法で失敗しても、別の方法を模索。
成功に辿り着くルートを探し出して。
その過程でぶつかる問題を予想しながら、対策を立てて。

「行動➡︎検証➡︎改善」の繰り返し
実行力に優れた人とは?
楽観的な思考と、悲観的な考えを同時に持っている人。
両面的思考を手にいれるプロセス
①望みを手に入れた自分の姿をイメージ。
どのようなメリットを得られるかを最大限に探し出して。
②目標達成へのプロセスでぶつかる難問や突発的な事態を、予想。
③それらの問題に、効果的に対処できる対策を立てて。
成功のコツ
まねる。
既に成功している人の習慣、方法を研究して。

努力の方向性を間違えないためにも。

守・破・離という言葉もあります。
最初は、オリジナルは入れず、ひたすら真似を。
基礎大事。
本当の問題を見つける

問題解決の5つのステップ。
英語の頭文字をとって、IDEALステップというそうです。
①Identify the Problem
②Define the Problem
③Explore Solutions
④Act on Your Plan
⑤Look at the Effects
①問題を認識する
まず、「問題がある」という事実を、きちんと認識。

自分の失敗を認めるということも含めて。
まずは、気づくことがスタート地点。
問題を解決する必要性が感じられず、解決方法を探すこともできず。

適切な問いがなければ、求める答えは得られず。
問題ではないことを解決するために、多くの時間とエネルギーを浪費
解決すべき問題が何かを知るために、十分な時間をかけるとのこと。

正しい方向性を見極めて、生産性UPへ。
リソース(時間・資源)は有限。
大事なことだけに注力するためにも。
問題を正確に把握する前に、むやみに解決しようとしてあくせく。

行き当たりばったり。
無駄も多く。
②問題を把握する
問題があることを認めたら。
問題の本質を正確に把握。

行き当たりばったりの対応にならないように。
根本的解決を目指したいもの。
問題を繰り返さないように。

ボトルネックを探したいところ。
ボトルネックは、全体の円滑な進行・発展を妨げるような障害。
③解決策を探る
可能な限り、幅広く解決策を探って。
次に、長期的な観点から最善の解決策を選択。

トータルで見ると、良くなるような選択を。
短期では、損をするとしても。
④計画し、実行。
最終的な期限を含めた、実行可能な計画を立て、直ちに実行。
⑤結果を検討
結果を綿密に検討。
効果がなければ、、直ちに問題を再定義。
解決策を修正、補完。

検証、大事。
逆算スケジューリングを取り入れる
最終目標が、「今やるべきこと」を決める
スケジューリングには、基本的な2つの方法が。
現在を起点に。
順々に計算して、目標達成の時期を推定。
現時点から見ると、全てのことが重要に感じられるとのこと。
重要なことより、急ぎの用を選ぶ可能性が高くなりがち。
未来を起点に。
最終的に目標を達成する時期から逆算して、「今すぐ、すべきこと」を選択。
目標の達成を基準にして、逆方向から現在の状況を見ると、選択の幅はずっと狭く。
誘惑を振り切るのも簡単に。
目標と関係のないことを退けるのも容易に。
ストレスも減。

選択肢がない、少ないのは困りもの。
ありすぎるのも・・・。

最終目標に応じて、選択肢を選抜。
良い判断ができるように。
そして、大事なことだけに注力。
優先順位付けをしっかりと。
逆算スケジューリングの3ステップ
まず、達成したい目標と、最終的な期限を、はっきり定める。

「何をしたいか」がはっきりしていないと、迷走する羽目に。
意外とやりがち?

人間、締切があった方が頑張れる?
目標を達成するプロセスにおける、小目標と期限を定める。

目標に応じた段取りを、しっかり組みたいところ。
大きな課題は、分割して。
ラスボス倒すまでには、小ボス、中ボスを撃破して。
目標に関係する最初の仕事を選んで、直ちに実行。

やると決めたら。
あとは「やる or めっちゃやる」
「やらない」はなし。
リベラルアーツ大学、両学長曰く。
逆算スケジューリングは、人生のあらゆる分野で活用可能。
キャリア管理やビジネスだけでなく、健康管理や人間関係などでも。
どんな時も、「代案」を用意。
どんなに準備しても、突発的事態はやってくるもの。
突発的事態への備えが不可欠。
これをバックアップ・プラン、あるいは「プランB」というとのこと。

B案、C案を持っておきましょう。
緊急時の、対応の引き出しを準備。
説得の達人
常に「NO!」という答えを予想。
NOに対する代案を準備してから、相手に接近。
第2案が拒否された時に備えて、第3案を準備したり。

交渉事について。
できる人は、「NO」は「始まり」と考えるそうです。
終わりではなく。
目標達成のために
目標達成のための、具体的な実践計画(プランA)を考える。
実践のプロセスで、実践を妨害する突発事態を予想。
箇条書きに。
それぞれの事態に対する、代案(プランB)を考える。
可能なら、代案の代案(プランC)も考える。
プランBの3つの機能
突発事態を予想する習慣を持てば、不確実性への不安感が和らぐ。

想定外をどんどん減らしていければ。
対応策があれば、動じずに済む?
状況と自分自身を、コントロールする力が増強される。
予想される突発事態への対策を立てる過程で。
どんな状況でも、成果と満足感を味わう機会が増えるとのこと。
後悔と損失を味わう機会が減って。
状況と自分自身に対するコントロール力の増強により。

代案を持つことで、リスクコントロール。
対応の幅を広げていければ。
公開宣言効果を利用
人が言葉や文章で自分の考えを公開すると。
その考えを最後まで守ろうとする傾向が。

言霊という言葉もありますし。
公言して、引くに引けない状況を作ったり。
ビッグマウスも、使い様。
切実な理由を探す
どんな目標も。
切実な理由を探し出し、差し迫った気持ちで取り掛かれば、半分成功したようなもの。

「やるしかない」理由を見つけて。
「やらない」理由ではなく。

人生は、それまでの選択の積み重ね。
人生を変えたいなら、今とは違うことを選択、やるしかなく。
「いかに自分の人生に本気で向き合うか」が問われるところ。
自己動機化の3つのステップ
変えたい習慣や、実行したい決心を一つ探す。
変化しない場合に起こりそうな、恐ろしい状況を具体的にイメージ。
実行した時に起きるプラスの変化を想像しながら、アクションプランを立てる。
派生効果まで考える
目標を追求する過程で、目標達成後の派生効果まで考えることは、継続の力に。

起こるであろう、良い連鎖に注目。
「やるべき仕事」を「やりたい遊び」に変換。
将来にもたらされる結果を想像することで。

「やらされる」のは、楽しくないもの。
「やりたいこと」をやるのは楽しいもの。
後者に置き換えていきたいところ。
主体的にできるかどうか。
長期的な派生効果も生じるために、諦めにくく。
仕事が終わったら、すぐに報われるだけでなく。
自分が最後まで努力することで。

成功体験の積み重ねで、自信がつくかと。
実行する
・どうせやるなら、素早く処理を
・小さなことから始める
・終了だけでなく、開始にも締め切りを
・全ての行動を実験だと考える
・頼んだ人だけが助けてもらえる
・「観察の力」を利用する
・準備の時間は、短く
どうせやるなら、素早く処理を

「あれやらないと」と思い続けるのもストレスに。
脳のリソースも使い続けますし。
やるべきことはさっさとやって。
優先順位をつけつつ。
やらなくていいことは、やらないことを決めたり、外注したり。
固く決心したことが、後回しになる理由
・心の中に「実行したくない」という、強い拒否感が隠れているとのこと
・時間不一致現象
同じことでも、時間的距離によって、実行の難易度が違うように感じられる現象。
後で実行する計画に対しては、気持ちが大きくなりやすく。
すぐに実行に移すことは、難しく感じるとのこと。
成功している人は、反応が早い。

手紙やメールなどに対しても。
真似したいところ。
どんな状況でも、他人の好感と信頼を得ることが。
人は、相手がスピーディーに反応してくれる時、自分が尊重されていると感じるもの。
相手を信頼できる人だと判断するように。
速度は、自分を他人と差別化する最も効果的な手段。
アドバンテージを取るための、最も確実な要因。

レスポンスの速さは武器に。
即断即決の、自身へのメリット3つ
より重要なことを、より効率的に行うことができる。

考えることを減らすことで、良い判断ができるように。
自身のリソースは有限。
大事なことに注力できるように。
人生がより自由に。

「あれ、やらないと」も、脳のリソースを使用。
終わるまで、束縛されているようなもの。
ストレスにもなってしまいます。
望むものを、より多く得ることができる。
スピーディーな反応により、他人から信頼され、好感を持たれるため。

信頼の蓄積。
小さなことから始める
まず、簡単にできる、小さなことから始める

やる気は、やってるうちに出てくる面が。
達成難易度の低い、小さな成功体験を積むことによっても。
精神医学者のエミール・クレペリンさんによると。
人間の脳は、体が一旦動き始めると、止まるのにもエネルギーを消耗。
していることを続けるのが、より合理的と判断することが。
やりたいくないことでも、一旦始めると、集中できるように。
脳が刺激を受けて。

始めさえすれば、慣性が働くようなもの。
呼び水効果もあったり。
例:食べ物
そんなにお腹が減ってなくても。
少し食べると止まらなく。
変化は連鎖する
全ての変化は、自然と動く自己推進力を持っているとのこと。
ごく小さな変化が、次の変化を呼ぶことに。

大きな変化は、日々の積み重ねから。
行動修正の方法
行動モメンタム技能3ステップ
目標に関係することを、難しさの程度に従って順序づけ。
一番簡単なことから始める。
嫌になったら、いつでも辞めると考えながら。

継続するのが大事。
ハードルを上げすぎないように。
課題を小さく分解するのも手。
一定期間頑張って、習慣化できれば。
やらないことが逆に気持ち悪くなるように。
ある瞬間、意外に多くのことを成し遂げた自分の姿を確認して驚く。

行動にも複利が効きます。
厚切りジェイソンさんによると。
毎日0.1%よくなるか、悪くなるかとして。
1年間続くと重なって。
44%スキルアップ、または30.6%スキルダウンだとか。
早く始めて、継続するのが大事。
終了だけでなく、開始にも締め切りを
他人から与えられた締め切りを、自分が設定した締め切りに置き換えて。

自分の人生をコントロールすることにも。
締め切りは、人を必死にさせる

人間、時間に余裕があると、脇道にそれがち。
完璧主義に走ったり。
求められること以上の、オーバースペック状態になったり。
80点取れれば良いことが、ほとんどなのに。
まずは完成させるのを目指して。
締め切りを最大限に活用する3つの原則
小さなことから、一つずつ。
はっきりと、定義。

具体的な時間や、場所など。
重要な仕事をする時は、締め切りを公開。

公開することで、決心の撤回は難しく。
締め切り再設定の3ステップ
終了の締め切りを再設定する。
与えられた締め切りを前倒し。
自分だけの締め切りを設定。

自分でコントロール。
中間の締め切りを作る。
最終目標を、小さく分割。
それぞれの中間の締め切りを設定。
仕事のプレッシャーを減らして。

例えば。
一気に大掃除するよりも。
普段から、こまめに掃除している方が楽。
何事も、溜め込みすぎると大変。
開始の締め切りを定め、実践。
すぐに始められるような、初歩的な小さな仕事を探して。
開始の締め切りに合わせて実行。
全ての行動を、実験だと考える
仮説が間違っていたという、事実を教えてくれるもの。
新しい仮説が必要なことを悟らせてくれる、もう一つの成功体験。

自分で課題を見つけて、仮説を立て、実践、検証。
様々なことを、実験だと捉えて。

失敗で学ぶことも多々。
致命傷を負わず、最速で失敗して改善していくのが、近道。
できない理由を並べる前に、実際にやってみるのが大事
やりもせず、最初から駄目だろうと決めつけずに。

検討に時間をかけ過ぎずに。
まずはやってみて。
ダメなら、軌道修正すれば良いだけ。
実験精神が優れている3つの理由
実験は、失敗を当然と考える。
もし失敗しても。
それによって仮説の間違いをきちんと検証できる。

次に繋がるので、失敗を恐れなくなり。
失敗も、成功への必要経費と考えば。
世の中、やってみないとわからないことも多々。
実験とは、古い知識や理論を、新しいものに置き換えること。
実験精神を持てば、固定観念が破られ、視野が広くなり、柔軟性と創造性が向上。

時には常識を疑って。
0ベースで考えることも大事。
実験は、仮説を検証するプロセス。
ある現象をよく観察し、様々な条件を人為的につくって。
そのため、自分と現実をうまくコントロールできるとのこと。

客観視できるのがいい?
頼んだ人だけが、助けてもらえる。
自分より先に、問題を解決した人を探して、その人に教えを乞うこと。

成功している人の真似をするのは大事。
オリジナルは、後の方が無難かと。
自分を助けてくれる人がいないのは?
①助けを求めなかったから
考えは、適切に表現した時に、初めて相手に伝わるもの。

そもそも、頼まないと、助けてもらえないことが。
②助けを求める方法が、適切ではなかったから。
頼まれる側の立場に立って、助けたくなる理由、助けるべき理由を提示する必要が。

みんな忙しいもの。
助けた甲斐を感じてもらえるようにしないと。
助けてあげた時に、気持ちいい人の3つの特徴
助けを求める前に、やってきた努力と実践のプロセスを知らせてくれる。
心から尊重する気持ちと、謙遜の姿勢を、人一倍強く示す。
お返しを約束。
助けに対するフィードバックを提供し、感謝の気持ちを表す。
「観察の力」を利用する

変化を起こすには、まず認識・把握することから。
観察し、記録することで行動が変化
自分を含めて、誰かが行動を観察したり記録したりするだけでも、人の行動は変化。
反応を導き出すために、自分の行動を観察・記録して、行動を修正する技法。
変化が起こる理由
行動を観察すること自体が、その行動をより良い方向へと変化させる傾向があるとのこと。

意識するのが大事。
意識すると、問題解決へのアンテナも自然と立つように。
それまで、気づかなかったことに気づくようになるかと。
観察することで、行動に影響を与える原因を突き止めて。
自分をより効果的に管理することができるように。

改善すべき問題・課題を発見・認識。
観察の結果が、フィードバックやねぎらいに。
・得られたデータを元に、より有利な戦略を探し出せる。
・問題が深刻になる前に、手を打つことができる。
自己観察の3ステップ
自分の行動をしっかり見つめていれば、横道にそれず。
実行を忘れることもなく。
数値で記録した結果をグラフに。
実践結果を目で確かめられると、変化が起こりやすく。
変化の過程を公開すれば、諦めにくく。
アドバイスや励ましをもらえることも。
準備の時間は、短く
本当は重要だけれども、やりたくない仕事(頭を使う仕事)がある時。
単純な仕事(頭をあまり使わない仕事)をすることで、人はストレスから逃げる傾向が。

例えば。
勉強しないといけないのに、掃除ばっかりしたり。
やるべきことを、やりたくない。

一見、一生懸命にやっていることも。
別のやりたくないことをやらないための、怠惰の現れの場合が。
重要な仕事から逃げるために、不必要な仕事を作ったり。
重要でないことに気持ちがとらわれる、3つの理由
明確な目標がなければ、重要なことと、そうでないことの区別がつかず。

「最終的にどうしたいか」がないと、優先順位もつけれず。
目標に応じて、取るべき行動も変わるはず。
重要でないことでも、それなりのもっともらしい意味が。
その大部分は、簡単で楽しく。
重要なことから逃げながらも、自分は一生懸命だという言い訳を与えてくれる。

②③は、やらないことの免罪符にしてしまいがち?
整理整頓で、仕事をさっと始めるための環境づくり
必要のない物を、片付けたり、捨てたりすること。

仕事を妨げる誘惑になるものは、除外。
まずは断捨離から。
必要なものだけに囲まれるのが理想かと。
必要な物を、使いやすく並べること。

物を探す・取り出す時間を減らせれば。
チリも積もればなんとやら。
加えて、次の仕事の準備もしておくといいとのこと。

環境整備は大事。
整理整頓、準備や整備。
脳のリソースは有限。
判断回数を減らして、良い判断をしていくためにも。
準備の時間を減らす、3ステップ
「自分が逃げている、本当に重要な仕事は何か?」と自問自答。
やるべきこと、まずやるように。

例えば。
勉強してから、机を整理。
重要な仕事をすぐに始められない原因を取り除く。
仕事が終わったら、翌日に重要な仕事をすぐに始められるように準備を。
努力の方向性は、合っているか?
経営コンサルタントのデニス・ウェイトリーさんによると。
「失敗する人は常に緊張を解くための仕事をし、勝利する人は目標を勝ち取るための仕事をする」

せっかくの努力も、方向性を間違うと、無駄になりかねず。
維持する
・人はセルフイメージ通りの人間になる
・断る勇気を持つ
・自分ではなく、環境をコントロール
・「効率」より、「効果」を優先。価値の高い仕事を
・ゴールについて考える時間を確保
・できるまで、やる
・教えることは、学ぶこと
人はセルフイメージ通りの人間になる
自分に対するイメージが、行動を決定。
さらには、運命まで決定。

変化には、まずは考え方。
考え方が良いと、行動も良いものに変化。
行動が良いと、やがて人生も良いものに変化。
理想に描く姿の人間として、自分イメージ。

人は、自分のイメージに合致するように行動するとのこと。
自己イメージを変えるための3ステップ
決心しながら実行に移せないでいることを一つ、思い浮かべる。
実行を妨げる障害物となっている自己イメージを、探してみる。
それを、変化への足がかりとなる自己イメージに、置き換える

セネカさんによると。
「何かができないということは、難しいからではなく。
難しいと思い込んで、やってみようとしないから。」
人間、壁・限界を、自分で作ってしまうことが。
断る勇気を持つ
決心を途中で諦めた人、実行を先延ばしにする人の共通点。
それは、気の進まない頼まれ事を、うまく断れないという点。
・愛されたい欲求
・拒否されることに対する恐れ
・自分を重要な人物だと信じたい傾向が強い
・優柔不断で、目標を持たずに生きている可能性が高い
断る勇気を持つ必要性、3点
断らないと。
重要な仕事ができずに、後悔することが多く。

全部は、できないもの。
トレードオフを意識する必要が。
相手に気を遣って、断りきれずに頼みを聞き続けると。
頼み事をした人に対して、無意識に腹を立てることに。
気の進まない頼み事を全部受けていると、他人に振り回されている気になるため。

やらされていると、嫌になってくるもの。
好きなことですら。

コメディアンのビル・コスビーさんによると。
「失敗のコツは、全ての人を喜ばせようと努力すること」だとか。
万人受けは、無理。
キッパリ断れる人の特徴3点
・人情を受け取りたい
・拒否されることに対する恐れ
覚悟をしていれば、決断も簡単に。
世間はそれほど自分を重要視していないことも、受け入れて。

断ることによる、結果を受け入れて。
自分がいなくても、なんとかなるもの。
どんな人生を送りたいかの目標がはっきり。
他の人の頼みに振り回されずに、誘惑をキッパリと退けることが。

「自分はどうしたいのか、どうなりたいのか」は、行動の指針に。
断るべき時には、はっきりNO!
望みを叶えて、幸せな人生を歩むために。
何を選択し、何を放棄するかをはっきり決めて。
自分の選択の結果に、責任を負うと考えて。

人生、選択の連続。
効果的に断る方法、3点
アポなし訪問や不当な依頼に対しては、理由は不要。
親しい人の頼みの場合は、理由をはっきり伝えるのがいいとのこと。

何かのついでに、ぼったくり商品を売られそうになったら。
「いりません。」だけでOK。
理由は不要。
あいまいだと、相手は聞いてくれるかもという希望を持つ可能性が。
相手の時間・他の機会を奪うことになるかも知れず。
依頼に対する拒否。
依頼した人に対する拒否ではなく。
落ち着いた口調で丁重にお断りを。
自分ではなく、環境をコントロール
自身をコントロールしている刺激の力を認識し、状況をコントロール

自分で状況をコントロールできなければ、状況に自分がコントロールされることに。
環境をコントロールすることによって、自分をコントロールする方法

背水の陣など。
退路を断って、やらざるを得ない状況に。
実行力に優れた人は、効果的な事前措置戦略を持っていることが多いとのこと。
意志力がずば抜けているというより。

例えば。
掃除をしたければ、人を家に招くなど。

色々と、良い仕組みを作って解決していきたいところ。
「効率」より、「効果」を優先。価値の高い仕事を。
効率と価値の違い
投資した努力と結果の比率。
仕事をどれだけ多く、どれだけ早くできるかで測定。
現実の成果や寄与度に直結する、中心的な役割の仕事をどれだけよくやったかという尺度。
効率が高い仕事をするということは、成果を出せる仕事・寄与度が高い仕事をやったということ。

効率と成果は、別次元の問題。
効率が高くても、成果が保証されるわけではなく。
優先すべきは、効果・成果。

努力も方向性を間違うと、報われず。
目指すは、高い効果&高い効率。
効果的な人が、自分にする問い
自分は今、どんな仕事をしているのか
自分がどんな仕事をしているか、点検しつつ。
自身の仕事は、成果や寄与度にどれほど直結しているか?
より効果が高い仕事がないか、常に探して。
仕事が満足に回っている時でも。
成果に結びつかないこと、妨げになるものは何か?
その代わりに、今後力を注ぐべきことは何か?
効果的な人は、常に期待値と結果を見比べ。
長期的な視点で、すべきでない仕事は減らして。
代わりに、付加価値と寄与度の高い仕事に、より多くの時間と努力を傾けて。

方向性はずれていないか?
日々、検証、改善。
生産性の向上目指して。
ゴールについて考える時間を確保
望むものと、それを手に入れる方法をについて、考える時間を増やすべき。
目標について、考え続ければ方法が見つかり。
やり続ければ、達成できるとのこと。

目的意識を持っていると、思わぬ所からヒントが得られるかも。
組み合わせが、解決の糸口になることが多々。
目標を達成できない人の特徴3点
目標に対する、切実な動機がない
誘惑に振り回されやすい
目標を忘れて過ごす時間が多い
できるまで、やる
人は失敗せず。
ただ、途中で辞めているだけとのこと。
チャレンジし続ければ、いつか臨界点がやってくるとのこと。
「この状態」から「あの状態」に突然変わる瞬間。
表向きには、目に見える変化がなくても、内側では少しずつ変化が。

諦めたら、そこで試合終了。
営業マンへの調査結果
アメリカのマーケティングリサーチ会社ダートネルの調査結果によると。
3度断られて諦める営業マン:88%
3度断られても諦めない営業マン:12%
売上の80%以上を占めるのは、3度断られても諦めない営業マンとのこと。

「NO」と言われてからが、スタート?
いかに顧客の不安や悩みを汲み取り、解決できるか。
動かない相手を説得する3ステップ
相手の身になって、考える。
まずは与えるものを探してみて。

先出しの精神。
臨界点を仮定するにしても、同じ方法を繰り返さないように。
大義名分と理由を提供。
人間は理由を求める存在。
教えることは、学ぶこと
最もしっかり学べるのは、他人に教える時。

当然のことながら、わかっていないと教えられず。
一つのアプローチで伝わらなければ、別の伝え方が必要に。
その際、本質がわかっていないと。
伝え方も試行錯誤して。
結果、より深い学びに。
まとめ
・プロセスを「見える化」する
・本当の問題を見つける
・逆算スケジューリングを取り入れる
・どんな時も、「代案」を用意
・公開宣言効果を利用
・切実な理由を探す

必ずやるべき目標をしっかり立てて。
・どうせやるなら、素早く処理を
・小さなことから始める
・終了だけでなく、開始にも締め切りを
・全ての行動を実験だと考える
・頼んだ人だけが助けてもらえる
・「観察の力」を利用する
・準備の時間は、短く

とにかく行動・実践。
・人はセルフイメージ通りの人間になる
・断る勇気を持つ
・自分ではなく、環境をコントロール
・「効率」より、「効果」を優先。価値の高い仕事を。
・ゴールについて考える時間を確保
・できるまで、やる
・教えることは、学ぶこと

できるまで継続。

「後回し、しないためには、やり方が。」
人生を、もっと楽しく、快適に。
では、ありがとうございました!


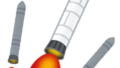
コメント